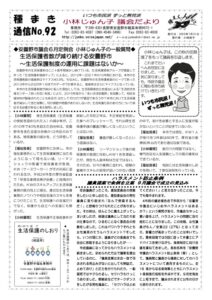子どもの『香害』および環境過敏症状に関する実態調査の第1報
~安曇野市の小中学校からの有効回答数532人~
日本臨床環境医学会環境過敏症分科会と室内環境学会環境過敏症分科会として、「香害」および環境過敏症の実態についてのアンケート調査を実施しました。ここに、香害をなくす議員の会も協力し、実態調査に参加してもらえるよう、教育委員会や学校に呼び掛けをしてきました。
「子どもの『香害』および環境過敏症状に関する実態調査」には、安曇野市の小中学校も参加しました。その調査報告の第1報が届きましたので、概要をお知らせします。
◆図1は、1.人工的な香りによる体調不良(香害)、2.化学物質過敏症状、3.電磁過敏症状について「あり」と回答した割合を、学年区分(小学校低学年・小学校高学年・中学生)ごとに集計した結果を示しています。
◆全国の結果をみると、1.人工的な香りによる体調不良(香害)と 2.化学物質過敏症状については、学年区分が上がるにつれて割合が高いこと、3.電磁過敏症状については、小学校高学年が高い割合となっています。
◆安曇野市では、1.人工的な香りによる体調不良(香害)と2.化学物質過敏症状については全学年区分において全国より割合が高く、3.電磁過敏症状については小学校低学年の割合のみ全国より低かったことが確認されました。
◆以上より、回答率が高くないため、割合そのものにあまり意味がないのかもしれませんが、安曇野市に限らず全国規模で、人工的な香りや化学物質、電磁発生源によって体調不良を訴える児童・生徒が一定数いることが確認できました。
◆寺田良一先生の分析では、未就学児で2%前後の「香害体調不良経験」が、成長ないし学校生活の継続とともに漸増し、小学校高学年以降は10%台に乗る。「不快」レベルの「香害」を含めれば、すでに多数の児童生徒が香害の被害を受けているといえる。体調不良として、吐き気、頭痛、脱力などが訴えられており、これらのかなりの部分が教室で体験されるので、香害で学習環境が損なわれている実態がうかがえる。学校教育環境の問題として、北米のフレグランス・フリー政策、より広く言えば公的空間のケミカルなバリアフリー化の推進が検討されるべき。との見解